はじめに
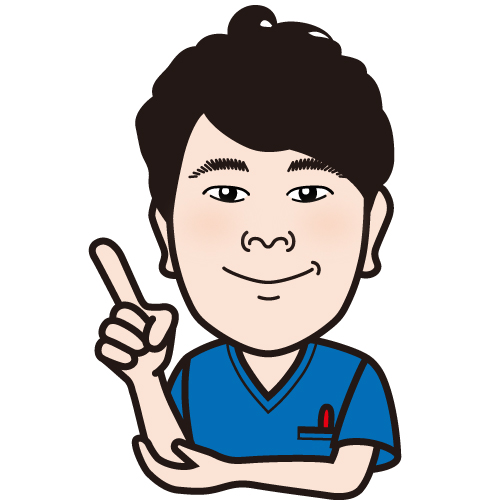
皆さんは「尿路感染症」という言葉を耳にしたことがありますか?
実は、風邪と同じくらい身近でありながら、軽く見てしまいがちな病気のひとつです。
放置して悪化すれば腎臓にまで炎症が広がることもあり、特に高齢の方や持病をお持ちの方にとっては注意が必要です。
この記事では、尿路感染症の種類とその特徴、症状、そして日常生活で気をつけたい予防策について、泌尿器科専門医の視点からわかりやすくご紹介します。
尿路感染症とは?
「尿路感染症」とは、尿の通り道である「尿路(腎臓・尿管・膀胱・尿道)」に細菌が感染する病気の総称です。
感染部位によって呼び名が異なり、それぞれ症状や重症度も異なります。
尿路感染症の主な種類と症状
① 膀胱炎(ぼうこうえん)
尿路感染症の中で最もよく見られるタイプです。女性に多く、特に若い女性や閉経後の方に多く見られます。
• 主な症状:排尿時の痛み(しみるような痛み)、頻尿、残尿感、下腹部の不快感
• 発熱はほとんどありませんが、放置すると腎盂腎炎に進行することもあります。
② 尿道炎(にょうどうえん)
主に性感染症(クラミジア、淋菌など)が原因で起こる尿道の感染です。男性に多くみられます。
• 主な症状:排尿時の灼熱感、膿のようなおりもの、かゆみ
• 女性ではあまり症状が目立たないこともあります。
③ 腎盂腎炎(じんうじんえん)
膀胱から上へと細菌がのぼり、腎臓の中まで炎症が及んだ状態です。高熱や背中の痛みが特徴で、早急な治療が必要です。
• 主な症状:高熱(38℃以上)、寒気、背部痛、吐き気
• 放置すると腎機能が損なわれることがあります。
④ 前立腺炎(ぜんりつせんえん)
男性特有の感染症で、尿道を通って前立腺に細菌が侵入し炎症を起こします。
• 主な症状:排尿痛、頻尿、会陰部の違和感、発熱
• 慢性化すると長期的な排尿トラブルの原因になることもあります。
なぜ感染するの? 尿路感染の原因とリスク
多くの場合、原因は大腸菌などの常在菌です。尿道から膀胱へと侵入し、繁殖することで感染を引き起こします。
感染しやすくなる状況
• 水分摂取不足(尿が濃くなり細菌が繁殖しやすい)
• 排尿を我慢する習慣
• 性行為後の洗浄不足
• 尿道カテーテルの留置
• 糖尿病や免疫力低下状態
泌尿器科でできること
尿路感染症が疑われる場合、泌尿器科では以下のような検査や治療を行います。
• 尿検査:白血球、細菌の有無を調べる基本検査
• 培養検査:どの細菌が原因か特定し、最適な抗菌薬を選定
• 超音波検査:腎臓や膀胱の状態を確認
• 治療:抗生物質の内服や点滴治療が中心です
症状が軽くても、適切な抗菌薬を選ぶことが重要であり、自己判断で市販薬に頼ると悪化することもあります。
予防のための5つのポイント
❶ こまめな水分補給
尿量を増やして細菌を洗い流しましょう。
❷ 排尿は我慢しない
尿が長時間膀胱にとどまると感染リスクが高まります。
❸ 性行為後の排尿や洗浄
特に女性は尿道が短く、感染しやすいため注意しましょう。
❹ トイレットペーパーの拭き方(前から後ろへ)
菌の逆流を防ぎます。
❺ 下着やナプキンを清潔に保つ
蒸れた環境は菌の温床になります。
泌尿器科専門医に相談すべきタイミングとは?
「少し痛いけど、我慢できるから…」と自己判断で放置するのは危険です。
以下のような症状がある場合は、早めに泌尿器科を受診してください。
• 排尿時の痛みが続く
• 発熱や腰の痛みがある
• 頻繁に膀胱炎を繰り返す
• 性感染症が心配
• 残尿感や違和感が長引いている
泌尿器科では、尿路感染症の早期発見・適切な治療に加え、再発予防の生活指導も行っています。
おわりに

尿路感染症は「誰にでも起こりうる身近な病気」です。
しかし正しく対処すれば、再発も予防でき、日常生活に支障をきたすことはありません。
少しでも不安な症状がある場合は、我慢せずに泌尿器科を受診してください。
早めの対処が、健康な毎日への第一歩です。
