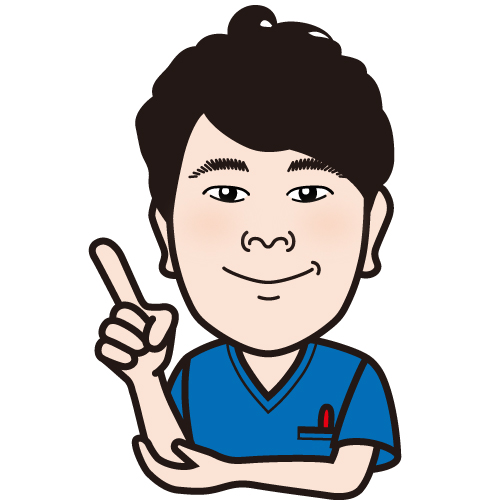
今回は、若い世代を中心に増加している性感染症(STD)の一つ、「尿道炎」についてお話しします。特に、クラミジアや淋菌といった細菌が原因となる感染性尿道炎は、性行為を通じて感染しやすく、自覚症状が少ないため見逃されやすい特徴があります。
「排尿時に少ししみる」「透明な膿のようなものが出る」
「なんとなく違和感があるけど、気のせいかも…」
こうした軽い違和感を放置すると、パートナーへの感染拡大や将来的な合併症につながることも。
この記事では、性行為に関連する尿道炎の原因や症状、治療法、そして何より「早期発見と予防の大切さ」について、泌尿器科専門医の立場からわかりやすくご紹介します。
尿道炎とは?
尿道炎とは、尿道(おしっこの通り道)に細菌やウイルスが感染して炎症が起きる状態です。
性行為によって感染するケースが多く、「性感染症(STD)」のひとつとして扱われます。
感染経路
• 性交(オーラル・膣・肛門性交を含む)
• 感染者との接触
• 不潔な環境や道具の共有(まれ)
主な原因菌はクラミジアと淋菌
1. クラミジア(Chlamydia trachomatis)
• 日本で最も多い性感染症の原因菌です。
• 細胞内に潜む特殊な菌で、症状が出にくいのが特徴。
• 男性では尿道炎、女性では子宮頸管炎、卵管炎の原因になります。
2. 淋菌(Neisseria gonorrhoeae)
• 感染力が非常に強く、性行為1回で感染するリスクは20〜50%とも。
• クラミジアよりも症状が強く出やすい傾向があります。
• 放置すると、女性では骨盤内感染を引き起こすことも。
こんな症状があったら要注意
男性の症状
• 排尿時の痛み・しみる感じ(特に朝方)
• 透明〜白色の分泌物(膿)
• かゆみ、違和感、ムズムズ感
• 尿道の先が赤くなる、腫れる
女性の症状
• おりものの増加や異臭
• 軽い下腹部痛
• 性交痛や不正出血
• 排尿時の違和感(症状が乏しいことも)
ポイント:女性は無症状のまま感染を持っていることが多く、知らずにパートナーにうつすこともあります。
泌尿器科での検査と診断
尿道炎が疑われる場合、泌尿器科では以下のような検査を行います。
1. 問診・診察(事前にWEB問診も可能)
• 性交の有無や相手の感染歴、症状の経過を確認。
2. 尿検査(第一尿:朝一番の尿がベスト)
• 白血球や菌の存在をチェック。
• PCR検査でクラミジア・淋菌を高精度で検出(こちらは外注検査となります)
3. 尿道分泌物の検査(必要に応じて)
• 尿道から分泌物を採取して培養検査。
治療は抗菌薬
クラミジアや淋菌による尿道炎は、適切な抗菌薬を使えばほとんどが完治します。
治療薬の一例
• クラミジア:アジスロマイシン(1回の内服)またはドキシサイクリン(7日間内服)
• 淋菌:セフトリアキソン(注射)、アジスロマイシン(1回の内服)など
大事なポイント:「パートナーも一緒に治療」
感染している本人だけでなく、パートナーも同時に治療しないと再感染を繰り返すことになります。
放置するとどうなる?
女性の場合
• 骨盤内炎症性疾患(PID)
• 卵管炎・卵管閉塞 → 将来の不妊症や子宮外妊娠の原因に
軽い症状で済ませず、泌尿器科や婦人科で早めに検査・治療を受けましょう。
予防のための3つの心得
性感染症による尿道炎を防ぐには、正しい知識と予防行動が何より大切です。
1. コンドームの使用を習慣に
性行為の際は必ず使用する。オーラルでも感染リスクはあります。
2. 定期的な検査を受ける
無症状のことが多いため、症状がなくても年1回は検査を。
3. 不特定多数との性行為を避ける
相手の感染歴がわからない場合は特に注意が必要です。
泌尿器科に相談しやすい雰囲気づくりを心がけています
「性のことを相談するのは恥ずかしい」「誰にも知られたくない」
そう感じる方は少なくありません。
当院では、
• 予約制でプライバシーを重視
• 院内では名前でなく番号でお呼びします
• 男女ともに相談しやすい対応
• パートナー同伴での相談も可能
といった環境づくりを大切にしています。
不安や疑問がある方も、安心してご来院ください。
おわりに

尿道炎は、ちょっとした違和感から始まることが多く、見逃されがちな病気です。
しかし、原因となる性感染症を放置すると、思わぬ合併症やパートナーへの感染につながります。
「これっておかしいかな?」と感じたら、迷わず泌尿器科へご相談ください。
性の悩みも含めて、専門医として真摯にサポートいたします。
健康な体と信頼できる関係を守るために、泌尿器科での早期受診をぜひご検討ください。
