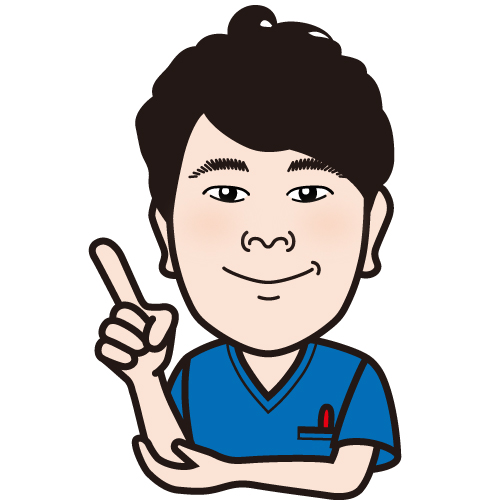
今回は、高齢者に多い尿路感染症の特徴と注意点についてご紹介します。
「最近、食欲がない」「なんとなく元気がなく、ぼーっとしている」「認知症が急に進んだような気がする」
こうした様子を見て、「年齢のせいかな」と思っていませんか?
実はその裏に、尿路感染症が隠れていることがあります。
高齢者は、若い人と違って典型的な症状が出にくいため、見逃されやすく、発見が遅れることも。
この記事では、高齢者における尿路感染症の症状の特徴や、泌尿器科でできる検査・治療、そしてご家族や介護者ができる予防策について、詳しく解説いたします。
高齢者に多い尿路感染症とは?
尿路感染症は、腎臓・尿管・膀胱・尿道といった「尿の通り道」に細菌が感染して炎症を起こす病気です。
高齢者では、
• 免疫力の低下
• 排尿機能の衰え
• 排尿後に尿が残る(残尿)
などが重なり、尿路感染症が起きやすいのです。
高齢者の尿路感染症は「発熱しない」が特徴
若い人の尿路感染症は「排尿時の痛み」や「高熱」といったわかりやすい症状が多いですが、高齢者では症状が非典型的です。
よくある “見逃しサイン” はこれ
• 食欲が落ちた
• 元気がない
• 眠ってばかりいる
• 急に認知症が進んだように見える
• 尿が濁っている、臭いが強い
• 転倒が増えた
• 意識がぼんやりしている(せん妄)
発熱が出るとは限らず、「なんとなくいつもと違う」ことが感染のサインであることが少なくありません。
原因となる主な要因は?
高齢者が尿路感染症を起こしやすい背景には、いくつかの要因があります。
排尿に関する問題
• 前立腺肥大症や神経因性膀胱による残尿
• 失禁やおむつ使用による皮膚・尿道口の汚染
• 膀胱カテーテル(バルーン)の留置
• 水分摂取不足による尿量の低下
身体的・社会的な要因
• 免疫機能の低下
• 認知症や寝たきりで症状を訴えにくい
• 自己管理の難しさ
• 服薬や持病の影響
特に膀胱カテーテルを長期間使用している方は、無症状でも菌が常在していることが多く、感染との見極めが必要です。
泌尿器科での検査と診断
高齢者の尿路感染症は、症状だけで判断するのが難しいため、検査がとても重要です。
主な検査内容
• 尿検査(尿中白血球、細菌、血尿など)
• 尿培養検査(どの菌が原因かを特定)
• 血液検査(炎症反応や腎機能の確認)
• 腹部エコー検査(膀胱に尿が残っていないか、腎臓に腫れはないか)
泌尿器科ではここがポイント
• 原因となる「残尿」や「前立腺肥大」の評価
• 体調や基礎疾患に応じた治療の選択
• 抗菌薬の適正使用(耐性菌への配慮)
高齢者における治療と注意点
尿路感染症と診断された場合、抗菌薬での治療が基本です。
ただし、高齢者では体の反応が鈍く、治療反応を見極めるのが難しいこともあります。
軽症の場合
• 抗菌薬の内服治療
• 水分摂取を促し、尿量を増やす
• 生活習慣の見直し
中等度~重症の場合
• 点滴による抗菌薬投与(通院または入院)
• 熱がないのに全身状態が悪い場合も注意
• 腎機能障害や脱水がある場合は入院が必要
※繰り返す場合は、超音波検査や残尿測定で基礎疾患の有無を調べることが大切です。
放置するとどうなる?
高齢者の尿路感染症は、進行が早く、次のような重篤な状態に至ることもあります。
• 敗血症(細菌が血液に入り全身にまわる)
• 腎盂腎炎から腎機能障害へ
• せん妄や認知症の急速な悪化
• 脱水や低栄養の悪化による寝たきり化
「なんとなく元気がない」を見逃さず、早めの診断・治療が高齢者の命と生活の質を守ります。
家族や介護者にできる予防と早期発見
見守りのポイント
• トイレの回数や様子の変化に気づく
• 尿の色・臭いをチェック
• 発熱がなくても「いつもと違う」様子を大切に
• 体を清潔に保ち、おむつや下着はこまめに交換
• 水分補給をしっかり(1日1000〜1500mlを目安に)
カテーテル管理が必要な方は
• 医療者の指導のもとで適切に管理
• 異臭や濁りが出たらすぐ相談
• 必要に応じて定期的な尿培養を行う
泌尿器科に相談するタイミング
以下のようなサインがあれば、泌尿器科への受診をおすすめします。
• 発熱はないが、急に元気がなくなった
• 食欲が落ち、反応が鈍くなった
• トイレに行く回数が増えた、または極端に減った
• 尿の色や臭いが明らかに変わった
• 以前に尿路感染症を繰り返している
• 在宅でカテーテルを使っている方の体調が不安定
泌尿器科では、単なる感染症の治療だけでなく、再発予防・排尿管理・生活支援まで幅広く対応しています。
おわりに

高齢者の尿路感染症は、症状が見えにくく、体の変化が「老化」と混同されがちです。
でも、ちょっとした変化に気づくことで、命を救うこともできるのです。
「最近なんだか元気がないな」と感じたときは、迷わず泌尿器科にご相談ください。
医療のプロの視点から、見えにくい病気をしっかりキャッチし、安心できる生活を支えていきます。
ご家族・介護スタッフの皆さまも、どうぞ遠慮なくご相談ください。
