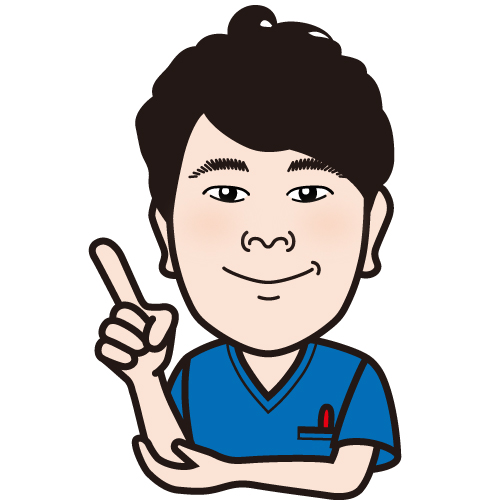
今回は、性感染症の中でも特に患者数が多く、若年層への影響が大きい「クラミジア感染症」についてお話しいたします。
テレビやネットで「クラミジア感染症は若者に多い」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは本当なのでしょうか?
実は、クラミジアは日本で最も多い性感染症のひとつであり、特に10代後半から20代の若い世代に多く見られます。自覚症状が出にくいという特徴があるため、気づかないうちに感染を広げてしまうこともあるのです。
今回は、クラミジア感染症の特徴やリスク、泌尿器科での対応について、わかりやすく解説いたします。
クラミジア感染症とは?
クラミジア感染症は、クラミジア・トラコマティスという細菌が原因で起こる性感染症です。
主に性行為(膣性交、口腔性交、肛門性交)を通じて感染し、男女ともにかかる可能性があります。
感染部位は性器だけでなく、咽頭(のど)や肛門におよぶこともあります。
一度感染しても、再感染することがあるため、注意が必要です。
若年層に多いのはなぜ?
① 自覚症状が少ない=気づかないまま感染が広がる
クラミジアは「サイレント感染症」と呼ばれることがあります。
つまり、自覚症状が出にくいため、感染していても気づかないまま性行為を続けてしまい、感染が広がってしまうのです。
特に女性は、感染していても症状が全く出ないことが多く、定期的に検査をしていない限り、発見が遅れることがあります。
② 性的接触の開始が早まっている傾向
近年、若年層における性体験の開始年齢が低下傾向にあることも、感染リスクの一因とされています。
初めての性行為で感染するケースも少なくなく、「自分は経験が少ないから大丈夫」という油断が危険です。
③ コンドームの使用率の低さ
若いカップルの中には、「避妊」のためには意識していても、性感染症の予防という観点からコンドームを使っていない場合があります。
「避妊している=安全」ではありません。
男性に多い症状と女性に多い症状
男性の場合(尿道クラミジア)
• 排尿時の痛み、かゆみ、違和感
• 透明〜白色の分泌物(膿)
• 尿道の不快感
ただし、症状が出ないこともあり、「ただの尿道炎かと思って放置していた」という方もいます。
女性の場合(子宮頸管クラミジア)
• おりものの量や色の変化
• 下腹部の痛み
• 不正出血(生理以外の出血)
女性の方が症状に気づきにくく、気づいたときにはすでに卵管炎や骨盤内炎症性疾患(PID)に進行していることもあります。
放置するとどうなるの?
クラミジア感染症を放置すると、以下のような重大な合併症を引き起こす可能性があります。
• 女性の場合:卵管の癒着、不妊症、子宮外妊娠のリスク
• 男性の場合:精巣上体炎による痛みや不妊リスク
• 男女ともに:咽頭感染や肛門感染による慢性炎症
また、妊婦さんが感染していると、出産時に赤ちゃんに感染して新生児肺炎や結膜炎の原因にもなります。
泌尿器科での検査と治療
検査方法は?
• 男性:尿検査が中心です(初尿を採取します)
• 女性:おりものや子宮頸部のぬぐい液、または尿検査
• 咽頭・肛門:綿棒によるぬぐい検体の採取
• 尿検査でクラミジアPCR検査を外注します(後日検査結果を説明します)
当院ではプライバシーに配慮した環境で検査を行っており、初診でもスムーズにご案内可能です。
治療
クラミジアは抗生物質(内服薬や点滴)で治療することができます。
多くの場合、1回の内服または数日の内服治療で改善しますが、パートナーの同時治療が非常に重要です。
感染の「再燃」や「再感染」を防ぐためにも、二人一緒に治療・検査を受けることをおすすめします。
感染予防のためにできること
• 性交渉時には必ずコンドームを使用する
• 不特定多数との性交渉を避ける
• 定期的に検査を受ける(特に若年層の方)
• 違和感があれば早めに受診する
性感染症は、誰にでも起こりうることです。
「まさか自分が」「そんなに経験がないから大丈夫」ではなく、“早く気づいて、早く治す”ことが大切です。
まとめ:若年層こそ、クラミジアに注意を

クラミジア感染症は、日本で最も多い性感染症のひとつであり、若年層に特に多く見られる傾向があります。
症状がないからといって安心せず、違和感があればすぐ泌尿器科へ。
また、定期的な検査も大切です。
当院では、性感染症の検査・治療を安心して受けられる環境を整えております。
おひとりでも、パートナーと一緒でも、お気軽にご相談ください。
