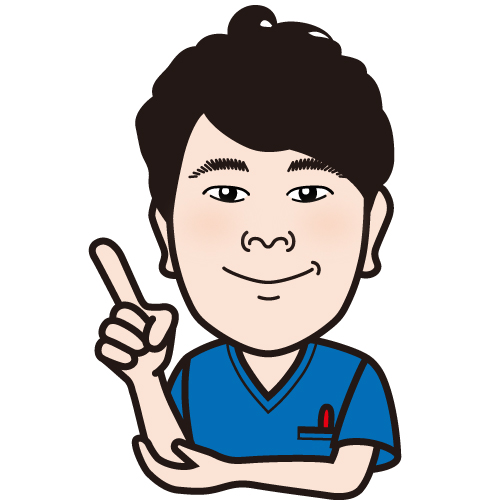
今回は「梅毒(ばいどく)」について、なぜ最近日本で患者数が増えているのか、その背景と具体的な対策をお伝えします。
梅毒は再び増えている!その現状とは?
増加する報告数
近年、日本国内で梅毒の報告数が急激に増加しており、2022年には記録的な1万名超(13,258例)を記録しました。2023年も約14,900名と報告があり、過去最多の水準が続いています
しかも、20代の女性と20〜50代の男性に特に多く、都市部での感染が目立っています
コロナ後の急増
新型コロナ禍では一時的に減少しましたが、2021年以降、感染が再燃。日本では特に増加率が高く、2021年は前年度比+36%、2022年はさらに+66%もの増加となりました。これは、豪州や中国と比較しても顕著な伸びです。
増えている理由は?主な要因を解説
① 性行動の変化と出会いの場
近年、出会い系アプリやSNSの普及により、「気軽な出会い」が増えました。これが梅毒などSTIの感染機会を増やす一因と考えられています。
特に、2012〜2014年頃からモバイルアプリ利用者を中心に感染が増加していたことも報告されています。
② コンドーム使用率の低下
性行為時にコンドームを使わないケースが増えており、避妊のみに意識が向いている傾向が見られます。これにより、 感染予防がおろそかになっている面があります。
③ コロナ禍による検査機会の減少
感染拡大の最中は外出・受診を控える人が増え、保健所やクリニックでの検査が減少していました。その結果、 発見が遅れ、結果的に感染を広めてしまった可能性もあります。
④ 風俗・性風俗業界の形態変化
2020年以降、「非店舗型」「派遣型」の性風俗サービスが増えています。検査や衛生管理が行き届きにくく、 感染リスクが高まっているという報告もあります。
なぜそれが重要なのか?梅毒の怖さ
無症状でも感染する
梅毒は「沈黙の感染症」と言われ、初期のしこり(硬性下疳)や発疹が消えると安心しがちですが、実際には進行している可能性があるのが厄介です。
重篤な合併症につながる
放置すると、数年後に心臓や神経を侵す「3期梅毒」になることもあります。妊婦さんが感染すると胎児にうつる「先天梅毒」も深刻な問題です。
具体的な対策と日常でできる予防策
1. 定期的に検査を受ける
とくに性的パートナーが多い方、出会い系アプリを使っている方は年に1〜2回、検査を受けることをおすすめします。妊娠を考えている方も早めの検査が重要です。
2. 正しいコンドーム使用
避妊だけでなく性感染症から自分を守るためにも、必ず使い方を正しく学んで、毎回着用を心がけてください。
3. 症状に敏感になる
小さなしこりや、発疹、のどや肛門の違和感など、少しでも気になることがあれば、すぐに泌尿器科専門医に相談してください。
4. 風俗利用時の衛生意識を高める
性風俗サービスを利用する場合は、信頼できる店舗を選ぶ、コンドーム使用を確認する、検査を定期的に受けるなど、セルフケアを大切にしましょう。
泌尿器科でできること、ご相談ください
当院では、外注にて血液検査による梅毒の正確な診断、またペニシリン筋注などによる治療体制を整えています
また、プライバシーに配慮し、院内ではすべて番号にて患者さんをお呼びしますので、患者さんのお名前を待合室、会計等で呼ぶことはございません。
パートナーがいる方は、お互いに検査・治療を一緒に受けることも重要です。再感染や感染拡大を防ぎましょう。
まとめ:知らないままだと危険も。早めの検査が安心への第一歩

• 梅毒は近年、特に若年女性と20〜50代男性で再流行中。
• 増加の背景には、出会い系アプリ使用、コンドーム不足、コロナによる検査機会減少、非店舗型風俗の増加など複合的理由があります。
• 無症状で進行する危険性や、将来的な重篤合併症・先天感染の問題も。
• 定期検査、正しいコンドーム使用、小さな症状でも受診、風俗利用時の衛生意識が予防のポイント。
• 当院では安心・確実な検査治療が可能です。迷ったらまずはご相談ください。
